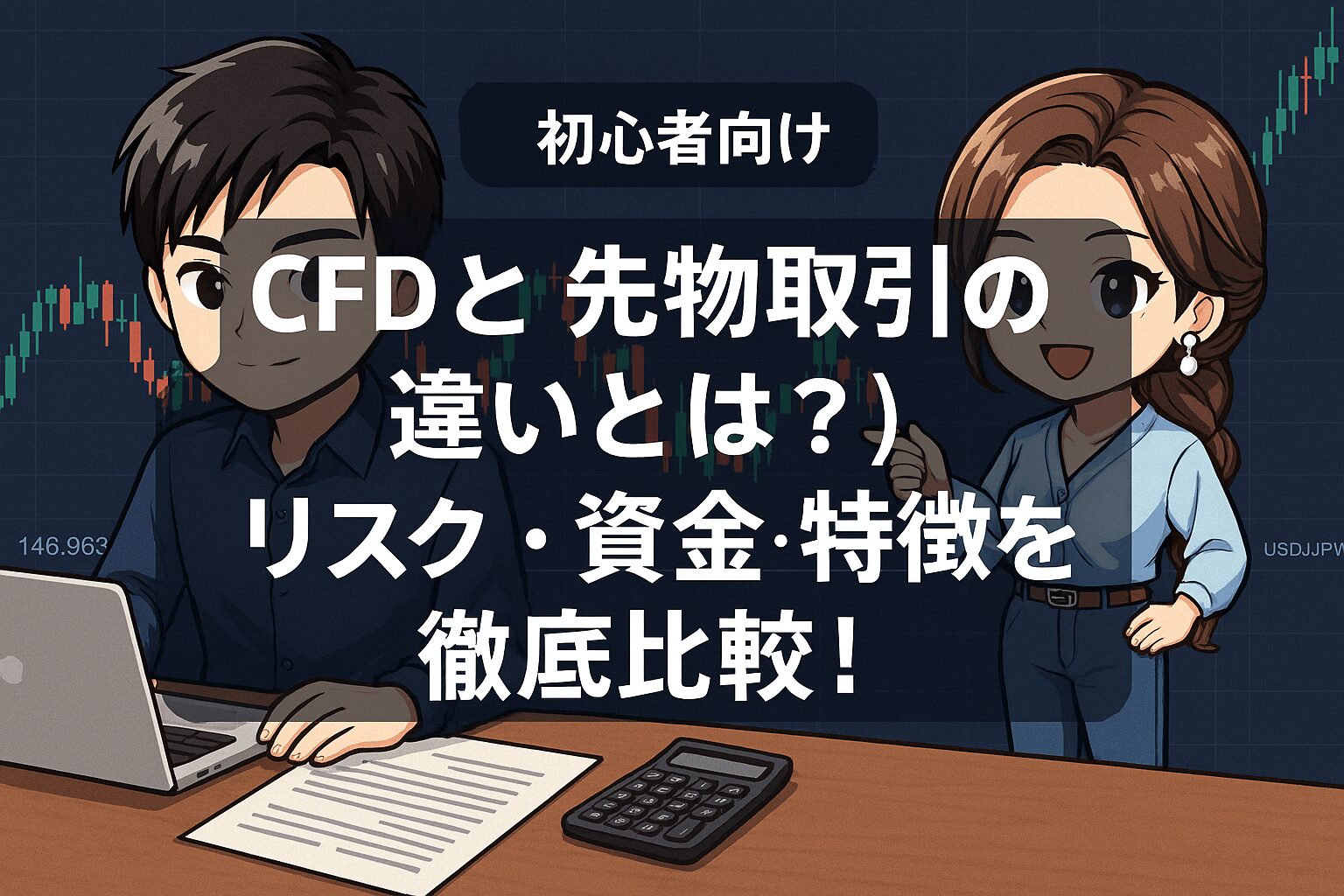CFDと先物取引の違い、特に初心者の方にとっては複雑に感じますよね。
この記事では、CFDと先物取引の基本的な仕組みから、コスト、リスク、必要な資金まで、あらゆる角度から徹底的に比較します。
この記事を読めば、あなたに最適な取引方法が明確になるでしょう。
以前、私もどちらを選ぶべきか悩みましたが、この記事の情報のおかげで、自分の投資スタイルに合ったCFD取引を見つけることができました。
あなたもこの記事を参考に、賢い投資判断をして、資産を増やしましょう。
1. CFDと先物取引の基礎理解
CFD(差金決済取引)と先物取引は、どちらも少ない資金で大きな取引ができる金融商品です。CFDは現物を実際に持つことなく、売買価格の差額で利益をねらう取引方法で、多くの場合、決済の期限がありません。一方、先物取引は将来の特定の日にあらかじめ決めた価格で売買することを約束する取引で、決済の期限(限月)が必ずあります。この章では、それぞれの基本的な仕組みと、主な共通点や違う点を分かりやすく説明します。
1.1 CFD(差金決済取引)とは
CFDは「Contract For Difference」という英語の頭文字をとったもので、日本語では「差金決済取引(さきんけっさいとりひき)」といいます。
これは、実際に株式や金、原油といった商品そのものを持つことなく、その価格が上がったり下がったりすることを利用して利益をねらう取引方法です。
取引を始めた時の価格と、終わった時の価格の差額が、利益になったり損失になったりします。
例えば、ある株価指数がこれから値上がりすると予想した場合、CFDで「買い」の注文を出し、予想通りに価格が上昇した時に「売り」の注文を出して決済することで、その差額が利益になります。
CFDでは、日本の日経平均株価(日本225などと呼ばれることもあります)やアメリカのダウ平均株価(米国30など)、さらには金や原油といった商品(コモディティ)など、さまざまな金融商品を取引の対象にできます。
CFDの主な特徴として、まずレバレッジ効果があります。
これは、少ない資金(これを証拠金といいます)を担保として預けることで、その何倍もの大きな金額の取引ができる仕組みです。
例えば、DMM CFDのような証券会社では、株価指数CFDなら10倍のレバレッジで取引できる場合があります。
次に、「売り」から取引を始められる点も特徴です。
通常の株式投資では、まず株を買ってから値上がりを待って売るのが一般的ですが、CFDでは価格が下がりそうだと予想した時に、先に「売り」の注文を出しておき、実際に価格が下がった時に「買い戻す」ことで利益をねらえます。
また、多くの証券会社ではCFDの取引手数料が無料となっています。
ただし、買いたい時の価格と売りたい時の価格には差(これをスプレッドといいます)があり、これが実質的な取引コストになる点には注意が必要です。
さらに、取引時間が長いこともCFDの魅力の一つです。
日本の株式市場が閉まっている夜間でも、海外の市場が開いていれば取引できる銘柄が多くあります。
そのため、日中お仕事などで忙しい方でも、ご自身の都合の良い時間に取引しやすいでしょう。
CFDの最も分かりやすい特徴は、「現物を持たない手軽さ」にあるといえます。
「差金決済」という名前の通り、取引するのはあくまで価格の差額だけで、実際の株券や金の延べ棒などが手元に来ることはありません。
これにより、現物を保管する手間やコストがかからず、純粋に価格の変動だけを対象に取引できるため、特に初心者の方にとっては取り組みやすい仕組みといえるでしょう。
そして、「売りから入れる」という柔軟性は、市場が上昇している時だけでなく、下落している時でも利益を得るチャンスがあることを意味します。
これは、従来の「安く買って高く売る」という一方向の考え方だけでなく、多様な市場の状況に対応できる投資の幅広さを提供してくれます。
CFDでは、世界中の株価指数や商品、さらには海外の個別企業の株など、非常に多くの種類の銘柄に一つの口座でアクセスできる便利さがあります。
しかし、選択肢が多いことは、初心者の方にとってはどれを選べばよいか迷う原因にもなりかねません。
そのため、初めのうちは、ニュースなどでよく耳にする日経平均株価のような、身近で馴染みのある指数から取引を始めてみるのが、市場の動きや取引の感覚を掴む上で効果的でしょう。







1.2 先物取引とは
先物取引とは、将来のあらかじめ決められた日(これを「期日(きじつ)」や「限月(げんげつ)」といいます)に、特定の商品(例えば、日経平均株価や金など)を、今日決めた価格で売買することを「約束」する取引です。
例えば、あるお店で売られている5万円の金貨を、手元にお金が足りないけれどどうしても欲しいと考えたとします。
そこで、お店と「1年後に、今の5万円という価格でこの金貨を買います」という約束をするようなイメージです。
1年後、もし金の価格が大きく値上がりして12万円になっていたとしても、約束通り5万円でその金貨を買うことができます。
この場合、7万円安く買えたことになります。
逆に、もし金の価格が3万円に値下がりしていたとしても、約束は約束なので5万円で買わなければなりません。
この場合は、実際の価値よりも2万円多く支払うことになります。
先物取引もCFDと同じように、価格が上がると思えば「買い」の約束を、価格が下がると思えば「売り」の約束をすることができます。
また、少ない資金(証拠金)で大きな取引ができるレバレッジを利用できる点も共通しています。
取引の対象となるのは、日経平均株価のような株価指数や、金・原油といった商品、国債のような債券などです。
先物取引が生まれた背景には、農産物を作る農家の人や、原材料を仕入れる企業などが、将来の価格変動によるリスクを避ける(ヘッジする)という目的がありました。
例えば、農家の方が豊作で価格が下がるのを心配して、あらかじめ一定の価格で売る約束をしておく、といった具合です。
現在では、このようなリスクヘッジの目的だけでなく、私たち個人投資家が価格の変動を予想して利益をねらう投機的な取引も活発に行われています。
ここで大切なのは、先物取引はあくまで「将来売買する約束」であるという点です。
これは、将来売買する「権利」を取引するオプション取引とは異なるものです。
そして、先物取引の最も大きな特徴の一つが、「期日(限月)」の存在です。
この期日が来ると、持っているポジション(約束)は自動的に決済されてしまいます。
たとえ損失を抱えている状態(含み損)であっても、自分の意思とは関係なく決済されてしまう可能性があるため、常に期日を意識した取引計画が必要になります。
これは、原則として決済期限のないCFDとの大きな違いといえるでしょう。
また、先物取引は差金決済で行われることが多いですが、取引する商品によっては、期日までポジションを持っていると実際にその商品を受け取ったり、引き渡したりする「現物の受け渡し」が発生する場合があります。
CFDでは現物の受け渡しは一切ないため、この点も異なります。









1.3 共通点と相違点の早わかり
CFDと先物取引、どちらも少し専門的な言葉が多くてむずかしく感じるかもしれません。
でも、基本的なポイントをおさえてしまえば、それぞれの特徴が分かってきます。
ここでは、二つの取引方法の似ている点(共通点)と、違う点(相違点)を、分かりやすく整理して比べてみましょう。
まず、CFDと先物取引の共通点から見ていきます。
一つ目は、どちらもレバレッジを使うことができる点です。
レバレッジとは「てこの原理」のことで、少ない資金(証拠金)を元手にして、それよりも大きな金額の取引ができます。
これにより、資金を効率よく使った投資が可能です。
二つ目は、「売り」から取引を始めることができる点です。
通常、株などを買う時は値段が上がることを期待しますが、CFDや先物取引では、値段が下がると思った時でも、先に「売り」の注文を出して利益をねらえます。
つまり、相場が上昇している局面だけでなく、下落している局面でも取引のチャンスがあるということです。
三つ目は、多くの個人投資家にとっては、差金決済が基本であるという点です。
これは、実際に商品そのもの(例えば株券や金の延べ棒など)を受け取ったり渡したりするのではなく、取引を始めた時の価格と終わった時の価格の差額だけを、お金でやり取りして取引を完了させる仕組みです。
次に、CFDと先物取引の相違点を比べてみましょう。
| 特徴 | CFD | 先物取引 |
| 主な目的 | 差額の利益を得る | 将来の価格で売買を約束する |
| 決済期限(限月) | 原則としてありません | 必ずあります |
| 現物の受渡し | ありません | ある場合もあります |
| 取引単位 | 比較的小さく、少額から始めやすい | 比較的大きく、まとまった資金が必要なことも |
| 取扱銘柄の種類 | 非常に豊富 | 主要なものが中心 |
| 取引手数料 | 無料の証券会社が多い | かかるのが一般的 |
| 取引の場 | 主に証券会社との店頭取引(OTC) | 主に取引所での取引 |
この比較表は、CFDと先物取引の主な違いをひと目で分かるようにしたものです。
特に、太字で示した「決済期限の有無」、「取引単位」、「取引手数料」は、どちらの取引方法を選ぶか考える上で大切なポイントになります。
例えば、「決済期限がない」CFDは、自分のペースでじっくり取引したい人に向いているかもしれません。
また、「取引単位が小さい」CFDは、初めは少ない金額から試してみたいという初心者の方にとって、始めやすい選択肢となるでしょう。
一方で、共通点として挙げた「レバレッジ」や「売りから入れる」といった便利な機能は、大きな利益をもたらす可能性がある反面、使い方を間違えると大きな損失につながる恐れもある「両刃の剣」です。
これらの機能を理解し、リスクをしっかり管理することが、どちらの取引を行う上でも非常にたいせつになります。
相違点の中でも、特に「決済期限の有無」と「取引単位の柔軟性」は、投資初心者の方がCFDを選ぶ際の大きな動機付けになることが多いポイントです。
決済期限に縛られずに自分のタイミングで取引を考えたい、あるいは、まずは少額から投資の世界に触れてみたい、という方にとっては、CFDの特性が魅力的にうつるでしょう。









2. 契約条件と取引メカニズムの違い
CFDと先物取引では、実際に取引を行う上での契約のルールや、取引が進んでいく仕組み(メカニズム)に、いくつかの大切な違いがあります。例えば、CFDは基本的に差金決済だけで、現物の商品を受け渡しすることはありませんが、先物取引には現物を受け渡す場合もあります。また、CFDには通常、いつまでに決済しなければならないという期限がありませんが、先物取引には「限月」という決済の期限がはっきりと決まっています。この章では、これらの差金決済と現物受渡しの違い、決済期限の有無、そして期限が来た時の対応であるロールオーバーや建玉の管理、さらには取引を始めるために必要な取引単位や最低資金について、具体的に見ていきましょう。
2.1 差金決済 vs 現物受渡し
CFD取引も先物取引も、基本的には「差金決済(さきんけっさい)」という方法で取引のけりをつけます。
これは、取引を始めた時の価格と、取引を終えた時の価格との「差額」だけを、お金でやり取りする仕組みのことです。
例えば、金のCFDを取引した場合、実際に金の延べ棒が送られてきたり、それをどこかに保管したりする必要はありません。
あくまで、金の価格が上がったか下がったか、その差額だけが損益として口座に反映されます。
利益が出ればその分のお金が口座に増え、損失が出ればその分のお金が口座から減る、というシンプルな仕組みです。
(1) 差額精算の仕組み
差金決済での差額の計算は、買いポジション(これから価格が上がると予想して買うこと)と売りポジション(これから価格が下がると予想して売ること)で少し異なります。
まず、買いポジションの場合を考えてみましょう。
基本は「安く買って高く売る」ことで利益をねらいます。
例えば、あるCFD銘柄の価格が100円の時に「買い」でポジションを持ったとします。
その後、予想通りに価格が上昇し、120円になった時にそのポジションを「売り」で決済したとしましょう。
この場合、売った価格(120円)から買った価格(100円)を引いた、20円が利益となります(実際にはスプレッドや手数料を考慮する必要があります)。
逆に、もし価格が90円に値下がりしてしまった時に売って決済した場合は、差額の10円(100円 – 90円)が損失となってしまいます。
次に、売りポジションの場合です。
こちらは「高く売って安く買い戻す」ことで利益をねらいます。
例えば、あるCFD銘柄の価格が100円の時に「売り」でポジションを持ったとします。
その後、予想通りに価格が下落し、80円になった時にそのポジションを「買い戻し」で決済したとしましょう。
この場合、売った価格(100円)から買い戻した価格(80円)を引いた、20円が利益となります。
逆に、もし価格が110円に値上がりしてしまった時に買い戻して決済した場合は、差額の10円(110円 – 100円)が損失となってしまいます。
このように、買った価格と売った価格(または売った価格と買い戻した価格)の差額を計算して損益を確定するのが、差金決済の基本的な仕組みです。
(2) 受渡義務と限月の有無
差金決済が基本であることは共通していますが、現物の受け渡し義務や決済期限(限月)の有無については、CFDと先物取引で明確な違いがあります。
まずCFDの場合です。
CFD取引では、現物(げんぶつ)の受け渡しは一切ありません。
つまり、金のCFDを取引しても、実際に金地金が自宅に送られてくることはありませんし、原油のCFDを取引しても、原油の樽をどこかに保管する必要もありません。
あくまで、取引画面上の数字として価格の差額を取引するだけです。
また、ほとんどのCFD銘柄には「限月(げんげつ)」、つまり決済しなければならない最終的な期限が設定されていません。
これは、一度持ったポジション(買いや売りの約束)を、投資家自身の判断で好きなタイミングまで持ち続けることができる、という意味です。
次に先物取引の場合です。
先物取引では、日経225先物のような株価指数先物の場合、最終的には差金決済されるのが一般的で、現物の受け渡しはありません。
しかし、金や原油、トウモロコシといった商品先物の中には、限月(最終取引日)までポジションを持っていると、実際にその現物を受け取るか、または引き渡す義務が生じるものがあります。
もちろん、多くの個人投資家は、このような現物の受け渡しを避けるため、限月が到来する前に反対売買(買いポジションなら転売、売りポジションなら買い戻し)を行って決済します。
そして、先物取引には必ず限月があります。
これは、その取引がいつ終了するかの期限が明確に決まっているということです。
この限月までに決済するか、あるいは次の限月の契約に乗り換える(これをロールオーバーといいます)必要があります。
CFDの「現物受渡しなし・原則限月なし」という組み合わせは、取引の純粋な「金融的な側面」だけを抽出していると考えることができます。
これにより、初心者の方にとっては、現物を管理する物理的な面倒さや、迫り来る期限へのプレッシャーを感じることなく、価格変動への投機という行為そのものに集中しやすい環境が提供されています。
一方で、先物取引における「現物受渡しの可能性」は、たとえ実際に受け渡しが発生しなくても、その取引の背景にある「実体経済とのつながり」を意識させるものです。
例えば、金の先物を取引する際には、その背景に宝飾品を作る業者や工業製品に使う企業などの実際の需要がある、という感覚は、市場をより深く理解する上で役立つことがあります。
CFDはその部分をある意味で省略しているため手軽ですが、市場の背景理解という点では一段階抽象的になるともいえます。









2.2 決済期限(限月)の有無
取引をいつまでに終えなければならないか、という「決済期限」は、CFDと先物取引を選ぶ上でとてもたいせつな違いの一つです。
先物取引では、この決済期限のことを特に「限月(げんげつ)」と呼びます。
(1) 先物の限月と強制決済
先物取引には、例えば「2024年9月限(くがつぎり)」や「2024年12月限(じゅうにがつぎり)」というように、必ず限月が設定されています。
これは、その月の特定の決められた日(これをSQ日や最終取引日などといいます)までに、持っているポジションを決済しなければならない、という意味です。
日本の日経225先物のような株価指数先物では、一般的に3月、6月、9月、12月が限月となることが多いです。
もし、この限月の最終取引日までに自分でポジションを決済しなかった場合、どうなるのでしょうか。
その場合、自動的にその時の市場価格で強制的に決済されてしまいます。
これは、たとえその時点で損失が出ている状態(いわゆる含み損)であっても、自分の意思とは関係なく損失が確定してしまう可能性があるということです。
この強制決済のリスクがあるため、先物取引を行う投資家は、常に限月を意識し、計画的に取引を行う必要があります。
(2) CFDの無期限ポジション
一方、ほとんどのCFD取引には、このような決済期限(限月)がありません。
これは、CFDの大きな特徴であり、メリットの一つといえるでしょう。
決済期限がないということは、一度持ったポジション(買いや売りの約束)を、投資家自身の判断で、好きなタイミングまで持ち続けることができるということです。
数日間だけ保有することも、数週間、数ヶ月、あるいはそれ以上の長期間保有することも、基本的には可能です(ただし、後で説明する保有コストや、一定以上の損失が出た場合の強制ロスカットには注意が必要です)。
このように決済期限に縛られないため、短期的な価格の細かな動きに一喜一憂することなく、じっくりと腰を据えた長期的な視点で投資戦略をたてることもできます。
市場の状況を見ながら、最適なタイミングを自分で判断して決済できるこの自由度の高さが、CFDが多くの投資家、特に初心者の方に選ばれる理由の一つとなっています。
CFDの「無期限ポジション」という特性は、投資を始めたばかりの初心者の方が、時間的な制約から解放され、ご自身のペースで市場の動きを学びながら取引経験を積んでいく上で、非常に有利な条件といえます。
先物取引のように限月が迫ってくると、「期限までに何とかしなければ」という焦りが生まれ、冷静な判断を妨げてしまう可能性があります。
CFDではこのような時間的なプレッシャーがないため、市場の動きをじっくりと観察し、自分の投資戦略を試してみる余裕が生まれます。
これは、投資の学習プロセスにおいて非常に大きなメリットです。
ただし、「無期限」であることには注意点もあります。
例えば、損失が出ているポジションを「いつか価格が戻るかもしれない」と期待して長期間持ち続けてしまい、結果的に損失をさらに拡大させてしまう、いわゆる「塩漬け」状態になるリスクです。
また、CFDではポジションを翌日に持ち越すと、金利調整額などの保有コストが発生する場合があるため、無期限に持ち続けることのコスト意識も必要になります。









2.3 ロールオーバーと建玉管理
「建玉(たてぎょく)」とは、まだ決済していない、保有中の買いポジションや売りポジションのことです。
この建玉をどのように管理していくかが、CFD取引や先物取引の成果に大きく影響します。
特に先物取引では、限月があるため、建玉管理において「ロールオーバー」という特有の手続きが必要になる場合があります。
(1) 先物の乗り換え手順
先物取引で、保有しているポジションの限月(決済期限)が近づいてきたけれど、まだそのポジションを持ち続けたい場合に行うのが「ロールオーバー」です。
具体的には、まず期近(きぢか=限月が近い)のポジションを決済し、それと同時に期先(きさき=限月がより遠い)の新しいポジションを建て直すという一連の作業を指します。
例えば、日経225先物の「9月限」の買いポジションを持っていて、9月の限月が近づいてきたとします。
しかし、まだ相場は上昇すると考えているため、この買いポジションを続けたい場合、まず「9月限」の買いポジションを売って決済します。
そして、それとほぼ同時に、新たに「12月限」など、次の限月の買いポジションを持つのです。
これにより、実質的に同じ買いポジションを持ち続けることができます。
ただし、このロールオーバーは投資家自身が行う必要があり、その際には決済と新規の取引で2回分の取引手数料がかかることが一般的です。
また、現在の限月の価格と次の限月の価格には、わずかな差(これを限月間スプレッドといいます)がある場合があり、その価格差も考慮に入れる必要があります。
(2) CFDの自動ロールオーバー
一方、先物商品を原資産(参照している元の金融商品)とするCFD、例えば日経225CFDや金CFDなどでは、このようなロールオーバーの手間が大きく軽減されています。
多くの場合、投資家が自分でロールオーバーの手続きをする必要はなく、証券会社が自動的に価格調整を行ってくれます。
これは、参照している先物市場で限月が交代するタイミング(例えば、9月限から12月限へ移る時など)に合わせて、CFDの価格も新しい限月の価格を反映するように調整される仕組みです。
この時に発生するのが「価格調整額」です。
価格調整額とは、古い限月のCFD価格と新しい限月のCFD価格の差によって、投資家の口座の資産評価額が有利になったり不利になったりしないように、その差額を調整するためのお金です。
この調整により、投資家は特に何もしなくても、実質的にポジションを持ち続けているのと同じような状態が保たれます。
価格調整額は、受け取りになることもあれば、支払いになることもあります。
これは損益ではなく、あくまで価格のズレを調整するためのものです。
(3) スプレッド拡大タイミングに注意
スプレッドとは、CFDを取引する際の買いたい時の価格(買値、アスクともいいます)と、売りたい時の価格(売値、ビッドともいいます)の差のことです。
このスプレッドが、CFD取引における実質的な取引コストの一つとなります。
通常、スプレッドは狭い方が投資家にとって有利ですが、市場の状況によってはこのスプレッドが一時的に大きく広がることがあります。
例えば、早朝や深夜など市場参加者が少ない時間帯、アメリカの雇用統計のような重要な経済指標の発表前後、あるいは市場が何らかのニュースで急激に価格変動している時などです。
また、CFDの価格調整(自動ロールオーバー)が行われるタイミングの前後でも、参照している先物市場の取引状況(例えば、限月交代に伴う取引量の急増など)により、一時的にCFDのスプレッドが通常よりも広がる可能性も考えられます。
スプレッドが広い時に取引してしまうと、思ったよりも不利な価格で取引が成立してしまう可能性があるため、注意が必要です。
CFDの「自動ロールオーバー(価格調整)」の仕組みは、先物取引における限月管理の複雑さや手間を大幅に軽減してくれるため、特に中長期的な視点でポジションを保有したいと考えている初心者の方にとっては、大きな利点といえるでしょう。
ただし、「価格調整額」という言葉やその仕組みは、初めての方には少し分かりにくいかもしれません。
大切なのは、これが市場の動きによる直接的な利益や損失ではなく、あくまでCFDの仕組み上、限月が交代することに伴う価格差の「調整」であると理解しておくことです。
また、スプレッドの変動リスクは、CFDの「取引手数料無料」というメリットの裏に隠れた実質的なコストであり、特に初心者の方が意識しづらい部分かもしれません。
「手数料無料」という言葉だけに注目するのではなく、スプレッドが実質的なコストであること、そしてそれが固定ではなく市場の状況によって変動することを理解しておくことが、賢い取引のためには重要です。









2.4 取引単位と最低必要資金
取引を始めるにあたって、「どれくらいの量から取引できるのか(取引単位)」そして「最低どれくらいの資金が必要なのか」は、特に初心者の方にとって気になるポイントでしょう。
CFDと先物取引では、これらの点にも違いがあります。
「取引単位」とは、1回の取引で売買する最小の量のことです。
例えば、株式なら「100株単位」といったものがありますが、CFDや先物取引でもそれぞれ最小の取引単位が決められています。
CFDの取引単位について見てみましょう。
CFDは一般的に、先物取引に比べて取引単位が小さく設定されていることが多いです。
例えば、日経平均株価を参照するCFDである「日本225」といった銘柄では、CFDの表示価格の10倍の金額から取引できる証券会社があります。
ある証券会社では、日経平均株価指数(JP225)が2万円の時に、最小取引単位である1単位から取引可能で、この場合の取引金額は2万円となります。
そして、レバレッジが10倍であれば、必要な証拠金はその10分の1の2,000円から取引を始められる、といった例もあります。
このように、CFDは比較的少額の資金から取引をスタートできるのが大きな特徴です。
次に、先物取引の取引単位です。
先物取引は、CFDに比べると取引単位が大きく、取引を始めるためにはある程度のまとまった資金が必要になる場合があります。
例えば、日経225先物には、取引単位が大きい「ラージ」と、その10分の1の「ミニ」、さらにミニの10分の1の「マイクロ」といった種類があります。
日経225先物(ミニ)の場合、日経平均株価の100倍の金額が1枚の取引単位となります。
仮に日経平均株価が30,000円だとすると、ミニ1枚の取引金額は300万円にもなります(レバレッジをかけるので、実際に300万円が必要なわけではありません)。
最近では、より少額から取引できるように「日経225マイクロ先物」も登場しており、これは日経225先物(ラージ)の100分の1の取引単位です。
例えば、ある時点での日経225マイクロ先物1枚あたりの必要証拠金が15,000円だった、という例もあります(これはあくまで一例で、証拠金額は変動します)。
最低必要資金の考え方としては、CFDも先物取引もレバレッジを利用するため、実際に取引する総額の全額を用意する必要はありません。
「証拠金」と呼ばれる、取引の担保となるお金を証券会社に預け入れることで、元手よりも大きな金額の取引が可能になります。
一般的に、CFDの方が取引単位をより細かく調整しやすく、より少ない証拠金で取引を始めやすい傾向にあります。
これは、特に投資初心者の方にとって、初めはリスクを抑えながら実際の取引経験を積んでいきたいというニーズに応えるものであり、大きなメリットといえるでしょう。
「少額から始められる」という手軽さは、CFDが初心者の方に広く推奨される大きな理由の一つです。
先物取引にも「ミニ」や「マイクロ」といった比較的小さな単位のものが登場していますが、それでもCFDの方がより柔軟に取引量を選びやすく、ご自身の資金額に合わせた細やかな調整がしやすい場合があります。









3. コスト・レバレッジ比較
CFD取引と先物取引を行う際には、いくつかのコストがかかります。また、どちらもレバレッジを利用できますが、その倍率や仕組みには違いがあります。この章では、取引に必要となる証拠金とレバレッジの倍率、取引手数料やスプレッドといった直接的なコスト構造、さらにはポジションを保有し続けることで発生する金利や価格調整額、そして最終的に利益が出た場合の税金の取り扱いについて、CFDと先物取引を比較しながら詳しく見ていきましょう。
3.1 必要証拠金とレバレッジ倍率
CFDや先物取引のように、少ない資金で大きな取引ができるのは「レバレッジ」という仕組みのおかげです。
そして、そのレバレッジを効かせた取引をするために、証券会社に預け入れる担保となるお金のことを「証拠金」といいます。
CFDの必要証拠金とレバレッジについてです。
CFDのレバレッジ倍率は、取引する商品や取り扱う証券会社によってあらかじめ決められています。
例えば、日本の株価指数CFDであれば最大10倍、金や原油などの商品CFDであれば最大20倍、海外の個別株CFDであれば最大5倍、といった具合です。
レバレッジが10倍の場合、100万円分の取引をするのに必要な証拠金は、その10分の1である10万円ということになります。
例えば、ある証券会社で日経平均株価を参照するCFD(日本N225)の価格が30,000円の時に、最小単位である1Lotを取引する場合、レバレッジが10倍だとすると、必要な証拠金は3,000円になる、という計算例があります。
先物取引の必要証拠金とレバレッジです。
先物取引のレバレッジ倍率は、CFDのように商品ごとに固定されているわけではなく、市場の価格変動の大きさ(ボラティリティ)など、さまざまな要因を考慮して計算される「SPAN(スパン)証拠金制度」という仕組みに基づいて、毎週見直され変動します。
一般的には、おおよそ20倍から30倍程度のレバレッジになることが多いといわれており、CFDよりも高いレバレッジで取引できる傾向があります。
例えば、ある時点での日経225ミニ先物1枚の取引に必要な証拠金が66,000円、より取引単位の小さい日経225マイクロ先物1枚であれば6,600円だった、という例があります。
レバレッジが高いことの注意点も理解しておく必要があります。
レバレッジが高いということは、少ない資金でより大きな利益をねらえる可能性がある一方で、予想が外れた場合には損失も同様に大きくなる可能性があるということです。
まさにハイリスク・ハイリターンな取引となりやすいため、特に投資初心者の方は、初めから高いレバレッジで取引するのではなく、レバレッジを低めに抑えるか、比較的レバレッジの低い商品を選ぶ方が安心でしょう。
その点では、先物取引に比べてレバレッジ倍率が低めに設定されていることが多いCFDは、初心者の方にとっては比較的リスクをコントロールしやすい取引といえるかもしれません。









3.2 取引手数料・スプレッド構造
取引を行う際には、必ず何らかのコストが発生します。
CFDと先物取引では、そのコストの構造に違いがあります。
まず、取引手数料についてです。
CFD取引の大きな特徴の一つとして、多くの証券会社で取引手数料が無料となっている点が挙げられます。
これは、取引の回数が多くなっても、その都度手数料を支払う必要がないため、コストを抑えやすいというメリットがあります。
一方、先物取引では、取引手数料がかかるのが一般的です。
この手数料の金額は、取引する証券会社や、日経225先物や金先物といった取引する商品によって異なります。
例えば、日経平均株価のミニ先物の場合、1枚あたり約30円前後の手数料がかかる、といった例があります。
次に、スプレッドについてです。
スプレッドとは、金融商品を取引する際の、買いたい時の価格(買値、アスク価格ともいいます)と、売りたい時の価格(売値、ビッド価格ともいいます)の差額のことです。
CFD取引では、このスプレッドが実質的な取引コストとして機能します。
例えば、あるCFD銘柄の買値が101円で、売値が100円だった場合、スプレッドは1円となります。
この場合、もしあなたが101円で買ってすぐに売ろうとしても、売値は100円なので、スプレッド分の1円の損失から取引がスタートすることになります。
このスプレッドは、常に一定ではなく、市場の流動性(取引の活発さ)が低い早朝や深夜、あるいは重要な経済指標の発表時などには、通常よりも広がることがあります。
先物取引にも、もちろん買値と売値の差であるスプレッドは存在しますが、CFDほど取引コストの中心として強く意識されることは少ないかもしれません。
コスト全体の比較を考えると、取引手数料が無料であることが多いCFDの方が、取引ごとにかかる直接的なコストは少ないといえるでしょう。
ただし、CFDの場合はスプレッドが実質的なコストとなるため、証券会社を選ぶ際には、できるだけスプレッドの狭い(買値と売値の差が小さい)ところを選ぶことが、トータルコストを抑える上で大切になります。









3.3 金利・価格調整額と保有コスト
CFDや先物取引でポジション(買いや売りの約束)を持った後、それを数日間以上保有し続ける場合には、さらに別の種類のコストが発生することがあります。
これを「保有コスト」といいます。
まず、CFDの保有コストについてです。
CFDでポジションを決済せずに翌営業日に持ち越す(これをオーバーナイトするといいます)と、「金利調整額」(オーバーナイト金利、ファンディングコスト、スワップポイントなどと呼ばれることもあります)が発生する場合があります。
これは、買いポジションを持っている場合は支払い、売りポジションを持っている場合は受け取りになることが多いですが、市場の金利情勢によってはこれが逆になることもあります。
FX(外国為替証券取引)のスワップポイントと似たようなものだと考えると分かりやすいでしょう。
この金利調整額が、CFDを長期間保有する際の主なコストの一つになります。
また、先物商品を原資産(もとになっている金融商品)とするCFD、例えば日経225CFDや原油CFDなどでは、参照している先物の限月(取引期限)が新しいものに切り替わる際に「価格調整額」が発生します。
これは、古い限月のCFD価格と新しい限月のCFD価格との間に生じる差を調整するためのもので、直接的な損益ではありません。
この価格調整額は、受け取りになることもあれば、支払いになることもあります。
さらに、株式CFDや株価指数CFDの場合、その原資産である株式に配当金の支払いなどがあった際には「権利調整額」(配当金相当額など)の受け払いが発生します。
買いポジションを持っていれば配当金に相当する金額を受け取れ、逆に売りポジションを持っていれば支払うことになります。
次に、先物取引の保有コストです。
先物取引の場合、CFDのような金利調整額といった形で日々発生する保有コストは、基本的にはありません。
ただし、先物取引には限月があるため、限月が近づいてきたポジションをさらに持ち続けたい場合には、「ロールオーバー」という次の限月の契約に乗り換える手続きが必要になります。
このロールオーバーの際には、既存のポジションを決済し、新たなポジションを建てるため、その都度、取引手数料がかかることがあります。
長期保有の視点で考えると、CFDを長期間保有する場合には、日々の金利調整額が積み重なっていくことを考慮に入れる必要があります。
一方、先物取引は日々発生するコストは少ないですが、定期的なロールオーバーの手間と、その際にかかる取引手数料が発生することを念頭に置く必要があります。









3.4 税制上の取り扱い
CFD取引や先物取引で利益が出た場合、その利益に対しては税金がかかります。
税金の仕組みは少し複雑に感じるかもしれませんが、基本的なポイントをおさえておきましょう。
まず、CFD取引の税金についてです。
個人の場合、CFD取引で得た利益は「雑所得(ざつしょとく)」という区分になり、「申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)」の対象となります。
申告分離課税とは、給与所得など他の所得とは合計せず、その利益だけで個別に税金を計算する方式です。
税率は、所得税が15%、住民税が5%、そして2037年12月31日までは復興特別所得税として所得税額の2.1%(つまり0.315%)が加算されるため、合計で20.315%となります。
この税金の取り扱いは、FX(外国為替証拠金取引)で得た利益と同じです。
次に、先物取引の税金です。
先物取引で得た利益も、CFD取引と同様に「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、税率も同じく合計20.315%です。
つまり、CFD取引も先物取引も、税金の計算方法や税率の面では基本的に同じ扱いということになります。
損益通算と繰越控除という制度も知っておくと役立ちます。
CFD取引や先物取引の損益は、同じ「先物取引に係る雑所得等」に分類される他の取引、例えばFX取引や他の商品先物取引などの損益と通算(つうさん)することができます。
これは、例えばCFD取引で100万円の利益が出たけれど、FX取引で30万円の損失が出た場合、それらを合算して70万円の利益として税金を計算できる、という意味です。
もし、年間の損益を通算した結果、損失の方が大きくなってしまった場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の利益から控除(こうじょ)する「繰越控除」という制度を利用できます。
ただし、この繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年にも確定申告を行う必要があります。
確定申告についてですが、CFD取引や先物取引で一定以上の利益が出た場合(例えば、会社員の方で給与所得以外の所得、つまりCFDや先物の利益などが年間で20万円を超えた場合など)は、原則としてご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告の期間は、通常、利益が出た年の翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
いくつか注意点があります。
株式の現物取引で得た利益(これを譲渡所得といいます)とは、税金の区分が異なるため、基本的にCFDや先物取引の損益と通算することはできません(ただし、一部の金融商品では例外もあります)。
また、税金のルールは法律の改正などによって変更されることがあるため、常に最新の情報を確認するように心がけましょう。









4. 取引環境の違い
CFD取引と先物取引では、実際にトレードを行う際の「環境」にもいくつかの違いがあります。例えば、取引できる時間帯や曜日、取引が実際に行われる場所が「取引所」なのか、それとも証券会社との「店頭」なのか、そして価格がどのように決まるのか、さらには市場でどれだけスムーズに取引できるかを示す「流動性」などです。これらの取引環境の違いを理解することは、自分に合った取引方法を選ぶ上でとてもたいせつです。この章では、これらの点をCFDと先物取引で比較しながら見ていきましょう。
4.1 取引時間と取引可能日
いつ取引できるか、というのは投資家にとって非常に重要なポイントです。
CFDの取引時間は、その大きな魅力の一つです。
銘柄によって異なりますが、ほぼ24時間取引できるものが多いのが特徴です。
例えば、日本の株式市場が閉まっている平日の夜間や早朝でも、アメリカの株価指数(ダウ平均やS&P500など)を参照するCFDや、金・原油といった商品CFDは活発に取引されています。
また、日本の祝祭日であっても、海外の市場が開いていれば取引可能な銘柄も多くあります。
このため、日中お仕事などで忙しい方でも、帰宅後の夜間やご自身の空いた時間に、比較的自由に取引タイミングを見つけやすいというメリットがあります。
一方、先物取引の取引時間は、その先物が上場している取引所によって明確に定められています。
日本の代表的な株価指数先物である日経225先物やTOPIX先物の場合、これらは大阪取引所(日本取引所グループ傘下)で取引されており、取引時間は大きく分けて日中取引と夜間取引があります。
日中取引は平日の午前8時45分から午後3時15分まで、夜間取引は同じく平日の午後4時30分から翌朝の午前5時30分まで(または午前6時までの場合も)というのが一般的です。
CFDに比べると、取引できない時間帯(例えば、日中取引終了から夜間取引開始までの間など)がはっきりと存在します。
取引可能日については、CFDは土日を除き、多くの銘柄で平日ほぼ毎日取引が可能です。
先物取引も基本的には、その取引所が開いている営業日に取引が行われます。
どちらが有利かという点で考えると、取引時間の長さや曜日をまたいだ柔軟性では、CFDの方が有利といえるでしょう。
世界中の様々な市場の動き(例えば、ヨーロッパ市場の開始やアメリカ市場の取引中の動きなど)に対して、よりリアルタイムに対応しやすく、結果として取引のチャンスも増える可能性があります。









4.2 取引所上場 vs 店頭取引(OTC)
CFDと先物取引では、実際に取引が行われる「場所」や「形態」にも違いがあります。
まず、取引所取引とは何かを説明します。
これは、日本取引所グループ(JPX)のような公的な「証券取引所」という市場で、不特定多数の買い手と売り手が集まって価格を決定し、取引を行う方法です。
取引のルールが明確に定められており、価格の透明性が高く、公正な取引が期待できるのが特徴です。
次に、店頭取引(OTC:Over The Counter の略)です。
これは、証券取引所のような公的な市場を介さずに、投資家とCFD業者などの金融機関が相対(あいたい)で、つまり1対1で直接取引を行う方法です。
取引価格は、その金融機関が提示するものを基準に取引します。
では、CFDの取引形態はどうでしょうか。
日本で提供されているCFD取引の多くは、この店頭取引(OTC)にあたります。
つまり、投資家はCFDを提供している証券会社やFX会社を相手方として取引を行うことになります。
ただし、「くりっく株365」のように、東京金融取引所に上場しているCFD(これを取引所CFDといいます)も存在します。
一方、先物取引の取引形態は、基本的にすべて取引所取引です。
日経225先物やTOPIX先物は大阪取引所で、金先物や原油先物などは東京商品取引所(TOCOM、現在は大阪取引所に移管・統合されているものも多い)といった公的な取引所で売買されています。
それぞれの形態には特徴があります。
店頭CFDの場合、CFD業者が顧客のニーズに合わせて比較的柔軟に商品設計(例えば、非常に多様な海外の株価指数や個別株のCFDを提供するなど)ができたり、独自の取引ツールや情報サービスを提供したりしやすいというメリットがあります。
一方で、価格の透明性や取引の公正性という点では、多くの参加者によって価格が形成される取引所取引に分があるという意見もあります。
ただし、現在の店頭CFD業者の多くは、参照している原市場(例えば、実際の株式市場や商品先物市場)の価格に基づいてレートを提示しており、その価格から大きくかけ離れた不透明な価格で取引が行われることは通常ありません。









4.3 価格決定メカニズムとスリッページ
CFDと先物取引では、取引する際の価格がどのように決まるのか、その仕組み(メカニズム)が少し異なります。
また、注文した価格と実際に取引が成立した価格がズレてしまう「スリッページ」という現象についても知っておく必要があります。
まず、価格決定の仕組みです。
店頭CFDの場合、取引する際の価格(買いたい時の価格と売りたい時の価格)は、基本的にそのCFDを提供している業者が提示する価格に基づいて決まります。
この業者が提示する価格は、そのCFDが参照している原資産(例えば、実際の株価指数や商品先物の市場価格など)の価格を参考にしていますが、完全に同一ではなく、業者ごとに若干の違いが生じることがあります。
一方、取引所CFD(くりっく株365など)や先物取引の場合、価格は取引所に集まる多くの買い注文と売り注文の状況、つまり需要と供給のバランスによって決まります。
これはオークション方式とも呼ばれ、買いたい人と売りたい人の希望価格が合致したところで取引が成立し、価格が決定されます。
次に、スリッページについてです。
スリッページとは、投資家が「この価格で買いたい(または売りたい)」と注文を出した時の価格と、実際に取引が成立(これを約定(やくじょう)といいます)した時の価格が、わずかにズレてしまう現象のことを指します。
特に、市場の価格が急激に大きく変動している時や、価格を指定しない「成行注文(なりゆきちゅうもん)」を出した時などに起こりやすいといわれています。
スリッページのリスクは、店頭CFDでも取引所取引でも、どちらでも発生する可能性があります。
もし、自分にとって不利な方向にスリッページしてしまうと、思ったよりも高い価格で買ってしまうことになったり、思ったよりも安い価格で売ってしまうことになったりする恐れがあります。
もちろん、逆に有利な方向にスリッページすることもありますが、それを期待するのは禁物です。
スリッページを完全に防ぐことは難しいですが、いくつかの対策によって、そのリスクをある程度抑えることが期待できます。
例えば、市場の価格変動が比較的穏やかな時に取引を行うことや、売買する価格をあらかじめ指定する「指値注文(さしねちゅうもん)」や「逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)」を上手に利用することなどです。
また、証券会社によっては、注文を出す際に許容できるスリッページの幅(許容スリッページ)を設定できる機能を提供している場合もあります。









4.4 流動性・板の厚さ
「流動性(りゅうどうせい)」や「板(いた)の厚さ」という言葉は、金融取引において非常にたいせつな概念です。
これらがCFDと先物取引でどのように異なるのかを見ていきましょう。
まず、流動性とは何かということです。
流動性とは、その市場で取引がどれだけ活発に行われているか、言い換えれば「売りたい時にすぐに売れるか」「買いたい時にすぐに買えるか」という、取引のしやすさの度合いを示す言葉です。
流動性が高い市場では、取引相手がすぐに見つかりやすく、自分の希望する価格に近い価格で売買できる可能性が高まります。
逆に、流動性が低い市場では、なかなか取引相手が見つからなかったり、自分の希望とはかけ離れた不利な価格で取引せざるを得なかったり、最悪の場合には取引自体が成立しないという恐れもあります。
次に、板(いた)情報とは何かです。
板情報とは、株式取引や先物取引などでよく見られるもので、どの価格帯にどれくらいの量の買い注文や売り注文が出されているかの一覧表のことです。
これを見ることで、その時点での市場の需要と供給のバランスや、各価格帯での注文の厚み(これが流動性の一部を示します)を把握する手がかりになります。
一般的に、各価格帯に多くの注文が出ている状態を「板が厚い」、注文が少ない状態を「板が薄い」といいます。板が厚いほど、流動性が高い傾向にあります。
では、CFDの流動性はどうでしょうか。
店頭CFDの場合、その流動性は主にCFDを提供している業者のカバー取引(顧客からの注文を処理するために業者が行う反対取引)の能力や、その業者を利用している他の顧客の取引量などに依存します。
日経平均株価やダウ平均株価といった人気の高い主要な株価指数CFDなどは、比較的流動性が高い傾向にありますが、あまり取引されていないマイナーな銘柄や、早朝や深夜など取引参加者が少ない時間帯は、流動性が低下することがあります。
流動性が低下すると、前述のスプレッド(買値と売値の差)が通常よりも広がりやすくなる傾向があります。
一方、先物取引の流動性です。
先物取引は取引所で行われるため、多くの市場参加者が存在します。
特に、日経225先物のような主要な銘柄の、中心となる限月(期近の限月)は、一般的に流動性が非常に高く、板も厚い傾向にあります。
ただし、限月がかなり先のマイナーな限月(これを期先限月といいます)や、あまり取引されていない銘柄、あるいは取引参加者が少ない時間帯(例えば、夜間取引の開始直後など)では、流動性が低くなることもあります。
流動性の重要性を改めて考えると、流動性はスムーズな取引と、適正な価格での取引成立のために非常にたいせつな要素です。
特に投資初心者の方は、初めのうちはできるだけ流動性の高い(つまり、よく取引されている)銘柄や時間帯を選んで取引する方が、予期せぬトラブルを避けやすく、安心して取引経験を積むことができるでしょう。









5. 取扱銘柄と市場アクセス
CFDと先物取引では、どのような種類の金融商品(銘柄)を取引できるのか、そして世界のどの市場にアクセスできるのかという点にも違いがあります。CFDは非常に多様な国の、さまざまな種類の資産に投資できるのが大きな特徴です。一方、先物取引は、各取引所に上場されている主要な株価指数や商品が中心となります。この章では、それぞれの取扱銘柄の特徴と、ご自身の投資目的(例えば、リスクを避けるためのヘッジ取引か、積極的に利益をねらう投機取引か)に合わせた市場の選び方について解説します。
5.1 CFDで取引できる資産クラス
CFD取引の最大の魅力の一つは、その取扱銘柄の圧倒的な豊富さにあるといえるでしょう。
一つのCFD口座を開設するだけで、日本国内だけでなく、世界中のさまざまな種類の資産(これを資産クラスといいます)に手軽に投資することが可能になります。
主な資産クラスとしては、以下のようなものがあります。
まず、株価指数CFDです。
これは、各国の株式市場全体の動きを示す株価指数を対象としたCFDです。
例えば、日本の日経平均株価(日本225などと表記されます)やTOPIX(東証株価指数)、アメリカのダウ工業株30種平均(米国30など)、S&P500種指数(米国500など)、ナスダック100指数(米国NAS100など)といった主要な指数はもちろんのこと、イギリスのFTSE100指数やドイツのDAX指数など、ヨーロッパやアジア各国の株価指数にも投資できます。
次に、商品CFD(コモディティCFD)です。
これは、金、銀、プラチナといった貴金属や、WTI原油やブレント原油といったエネルギー資源、さらにはトウモロコシや大豆、小麦といった農産物など、実体のある「商品」の価格変動に投資するものです。
そして、株式CFD(個別株CFD)もあります。
これは、個別の企業の株式を対象としたCFDで、日本国内の有名企業の株式だけでなく、アメリカのアップル社やグーグル社(アルファベット社)、アマゾン社といった世界的な大企業の株式や、ヨーロッパ、アジアなど海外の個別企業の株式も取引の対象となっています。
これにより、通常は海外の証券会社に口座を開かないと取引が難しいような外国株にも、日本のCFD口座を通じて手軽に投資できる道が開かれています。
その他にも、債券CFD(例えば、日本国債先物や米国債先物を参照するもの)や、特定の指数や商品などに連動するように設計された上場投資信託(ETF)を対象としたETF CFDなど、証券会社によってはさらに多様なCFDが提供されています。
このように、CFDは非常に幅広い投資対象をカバーしているため、投資家は自分の興味や分析、投資戦略に合わせて、世界中のさまざまな市場の動きから利益を得るチャンスを探ることができます。









5.2 先物で取引できる主要銘柄
先物取引で取引できる銘柄も多岐にわたりますが、CFDのように証券会社が自由に商品を設計できるわけではなく、各国の証券取引所や商品取引所に上場されているものが中心となります。
主な銘柄としては、以下のようなものがあります。
まず、株価指数先物です。
日本では、日経225先物(取引単位が大きいラージ、その10分の1のミニ、さらにミニの10分の1のマイクロがあります)や、TOPIX先物(こちらもラージとミニがあります)などが、最も代表的で取引量も多い株価指数先物です。
海外の取引所では、アメリカのS&P500先物やナスダック100先物、NYダウ先物なども非常に有名で、世界中の投資家によって活発に取引されています。
次に、商品先物です。
これは、金標準先物や金ミニ先物、プラチナ標準先物といった貴金属の先物や、原油先物、ゴム先物、そしてトウモロコシ先物や大豆先物といった農産物の先物など、古くから取引されている伝統的な商品が中心です。
日本では、これらの多くが東京商品取引所(TOCOM)などで取引されていましたが、現在は日本取引所グループ(JPX)の大阪取引所に多くの商品が移管・集約されています。
さらに、債券先物もあります。
主に、長期国債先物(標準物やミニ)などが取引されており、機関投資家などが金利変動リスクのヘッジなどに利用することが多いです。
その他にも、REIT(不動産投資信託)の価格指数に連動するREIT指数先物や、海外の取引所では短期金利や為替(通貨)の先物なども取引されています。
先物取引は、このように各市場を代表するような主要な銘柄が中心となっているのが特徴です。
CFDに比べると、特に海外の個別企業の株式や、新興国の株価指数、あるいは非常にニッチな商品などは、直接先物市場で取引することが難しい場合があります。









5.3 ヘッジ・投機に向く市場の選び方
CFDや先物取引を行う目的は、大きく分けて「ヘッジ取引」と「投機取引」の二つがあります。
それぞれの目的に応じて、どのような市場や銘柄を選ぶべきか考えてみましょう。
まず、ヘッジ取引とは何かということです。
ヘッジ取引とは、現在保有している資産(例えば、たくさんの現物株式や外貨など)の価格が、予期せぬ動きで下落(または上昇)してしまった場合の損失をカバー(軽減)するために、あらかじめ反対のポジションを取っておく取引のことです。
例えば、ある投資家が日本株の株式ポートフォリオ(複数の銘柄の組み合わせ)をたくさん持っているとします。
もし、これから日本全体の株価が下がりそうだと感じた場合、日経225先物や日経225CFDを「売り」で持っておくのです。
そうすれば、実際に株価が下落して保有株の価値が下がってしまっても、売っておいた先物やCFDの利益で、その損失の一部または全部を相殺できる可能性があります。
次に、投機取引とは何かです。
投機取引とは、ヘッジのような特定の資産を守る目的ではなく、純粋にこれからの価格の変動を予測して、その差益から利益を得ることをねらう取引のことです。
価格が上がるか下がるかを予想して、買いや売りのポジションを取ります。多くの個人投資家が行うのは、この投機取引が中心でしょう。
では、これらの目的に合わせて市場や銘柄をどのように選べばよいか、そのポイントを見ていきます。
ヘッジ目的の場合は、まず自分がヘッジしたい(守りたい)資産と、価格の動きが強く関連している(相関性が高い)市場や銘柄を選ぶことが非常に大切です。
例えば、前述のように日本株ポートフォリオのリスクをヘッジしたいのであれば、日本の株式市場全体の値動きをよく反映する日経225先物や日経225CFDが適しています。
また、ヘッジ取引を行う際には、できるだけ流動性が高く(取引が活発で)、ヘッジコスト(スプレッドや取引手数料など)が低い市場を選ぶと、より効率的にヘッジ効果を得やすくなります。
伝統的に、先物取引はこのようなヘッジ手段として、機関投資家などを中心によく利用されてきました。
投機目的の場合は、まず自分がよく知っている市場、あるいは情報収集がしやすい市場を選ぶのが基本です。
また、値動きの大きさ(これをボラティリティといいます)も考慮に入れると良いでしょう。
大きな値動きは大きな利益のチャンスをもたらしますが、同時に大きな損失のリスクも伴うため、自分のリスク許容度に合わせて選ぶ必要があります。
CFDは、その取扱銘柄の豊富さから、世界中のさまざまな市場のトレンドに乗った投機的な取引がしやすいといえます。
例えば、特定の国の経済成長に期待するならその国の株価指数CFDを選んだり、原油価格の今後の上昇を強く予想するなら原油CFDを選んだり、といった具体的な戦略が可能です。
また、少額から取引を始められるCFDは、さまざまな市場での投機取引を試してみる第一歩としても、取り組みやすいでしょう。
CFDと先物をどのように使い分けるかという点では、例えば、短期的な価格変動に対するヘッジや、細かな金額でのヘッジ調整には、取引単位が比較的小さく、柔軟な取引がしやすいCFDが向いている場合があります。
一方、伝統的なヘッジ戦略や、ある程度まとまった金額での大口の取引には、流動性が非常に高い主要な先物市場が選ばれることもあります。
投機目的で考えるならば、取引したい銘柄の種類の豊富さや、ほぼ24時間取引できるといった取引時間の長さから、CFDが有利な場面も多いと考えられます。
最終的には、ご自身の投資スタイル(短期売買か長期保有かなど)、使える資金額、そしてどれくらいのリスクなら受け入れられるか(リスク許容度)などを総合的に考えて、ご自身にとって最適な市場と金融商品を選ぶことが、成功への近道となるでしょう。









6. リスク管理ポイント
このセクションでは、CFD取引と先物取引に共通する、またはそれぞれに特有の重要なリスク管理ポイントを解説します。レバレッジの危険性、証拠金維持率の管理、ロスカット制度の役割と限界、そして期限到来による強制決済や価格変動・流動性といった市場リスクへの具体的な対処法を学びます。
6.1 レバレッジリスクと証拠金維持率
レバレッジとは、日本語で「てこの原理」を意味します。
少ない資金で、より大きな金額の取引ができる仕組みのことです。
例えば、10万円の資金があるとします。
10倍のレバレッジをかけると、100万円分の取引ができるようになります。
利益が大きくなる可能性があるのは魅力的でしょう。
しかし、損失も同じように大きくなる両刃の剣であることを忘れてはいけません。
証拠金とは、取引を行うためにFX会社や証券会社に預ける担保となるお金のことです。
証拠金維持率とは、取引に必要な証拠金に対して、口座にある純資産額がどのくらいの割合かを示す数値です。
計算式は「(純資産額-注文証拠金)÷ポジション必要証拠金×100」で求められます。
この維持率が、証券会社が定める一定のレベル、例えば100%や50%などを下回ると、追加で証拠金を入れる必要(追証)が生じます。
さらに下回ると、強制的に取引が終了されるロスカットが行われることもあります。
証拠金維持率が高いほど、レバレッジを抑えた取引となり、リスクは低くなります。
CFD取引では、銘柄によって最低必要証拠金率が異なります。
例えば、株価指数CFDでは10%、商品CFDでは5%、株式CFDでは20%といった具合です。
先物取引でも、SPAN証拠金という仕組みに基づいて必要な証拠金額が計算されます。
特に取引に慣れないうちは、高いレバレッジでの取引は避けるべきです。
常に余裕を持った資金で、証拠金維持率を高く保つように心がけましょう。
高いレバレッジをかけると、少しの値動きでも証拠金維持率が急激に低下しやすくなります。
そのため、ロスカットの危険性が高まるのです。
証拠金維持率は、ご自身の口座の安全度を示す大切なバロメーターだと考えて、こまめに確認する習慣をつけましょう。









6.2 ロスカット制度の有無
ロスカット制度とは、投資家の損失が一定の水準以上に拡大するのを防ぐための仕組みです。
保有しているポジションが、あらかじめ定められた損失のラインに達すると、自動的に決済されます。
CFD取引では、ほとんどの証券会社でこのロスカット制度が導入されています。
多くの場合、証拠金維持率が一定の割合、例えば50%を下回ったときに発動します。
証券会社によっては、保有しているポジションごとにロスカットレートが設定されることもあります。
先物取引にも、同様にロスカットルールが存在します。
証券会社によって基準は異なります。
例えば、有効証拠金が必要証拠金の90%を下回ると発動する、といったケースが見られます。
ロスカットは、損失の拡大を防ぐための安全装置のようなものです。
しかし、この制度も万能ではありません。
市場が非常に急激に変動したとき、例えば週末の大きなニュースで週明けの市場が窓を開けて始まるときなどです。
このような場合、設定していたロスカットレートよりも不利な価格で約定してしまうことがあります。
その結果、預けていた証拠金以上の損失が発生し、追加で資金を支払う必要(追証)が生じる可能性もゼロではないのです。
また、ロスカットは意図しないタイミングでポジションが決済されることになります。
そのため、ロスカットされた後に価格が戻ったとしても、その回復のチャンスを逃してしまう可能性も考えられます。
ロスカットがあるから安心と過信せず、ご自身でも損切り注文を設定するなど、主体的なリスク管理を心がけることが大切です。
ロスカットはあくまで最終防衛ラインであり、それに頼りきる取引は避けるべきでしょう。









6.3 期限到来による強制決済リスク
このリスクは、主に先物取引に特有のリスクと言えます。
先物取引には、「限月(げんげつ)」と呼ばれる取引の期限があらかじめ決められています。
例えば、日経225先物であれば、3月限、6月限、9月限、12月限といった具合です。
この限月が到来すると、保有しているポジションはSQ(特別清算指数)といった最終的な決済価格で自動的に決済されます。
もし、損失を抱えたままの状態で限月を迎えてしまうと、その損失が強制的に確定してしまいます。
反対に、利益が出ている場合でも、ご自身が望まないタイミングで決済されてしまうこともあり得ます。
一方で、CFD取引の多くは、このような取引期限(限月)が設けられていません。
そのため、理論上はポジションを無期限に保有し続けることが可能です。
もちろん、ポジションを保有し続けることによる金利調整額などのコストは発生します。
ただし、一部の株価指数CFDや商品CFDなどでは注意が必要です。
これらは参照している先物市場の限月に合わせて、CFDの限月も設定されている場合があります。
その場合、ロールオーバーという、古い限月のポジションを新しい限月のポジションに乗り換える作業が必要になり、その際に価格調整が行われることがあります。
この価格調整は、実質的な損益に影響を与えるため、理解しておく必要があります。
CFDの無期限性は大きなメリットですが、参照原資産によっては先物のような期限の概念が関わってくることを覚えておきましょう。









6.4 価格変動・流動性リスク
価格変動リスクとは、市場の価格がご自身の予測と反対の方向に動くことで、損失が発生する可能性のことです。
これはCFD取引や先物取引に限らず、株式投資や外国為替取引など、すべての投資に共通する基本的なリスクです。
特にレバレッジをかけて取引している場合は、この価格変動リスクが増幅されます。
少ない値動きでも、大きな利益または損失につながる可能性があるのです。
流動性リスクとは、取引したいときに、十分な取引量がない、または市場に参加している人が少ないために起こるリスクです。
具体的には、売りたいときにすぐに売れなかったり、買いたいときにすぐに買えなかったりすることがあります。
あるいは、希望する価格から大きく離れた、不利な価格でしか取引できない可能性も出てきます。
流動性が低い状況では、スプレッド、つまり売値と買値の差が通常よりも大きく開いてしまうことがあります。
また、注文が滑って(スリッページして)、意図しない価格で約定してしまうことも起こりやすくなります。
特に、早朝や深夜の時間帯、重要な経済指標が発表される前後、そしてあまり取引されていないマイナーな銘柄の取引では、流動性が低下しやすい傾向にあります。
CFD取引、特に店頭CFDの場合は、価格を提供する証券会社のカバー取引の状況によっても流動性が左右されることがあります。
先物取引でも、期近(きぢか)と呼ばれる限月が近いものに比べて、期先(きさき)と呼ばれる限月が遠いものの取引は流動性が低い場合があります。
また、あまり取引量の多くないマイナーな商品も同様に流動性が低いことがあります。
価格が有利に動いても、流動性がなければその利益を確定できないこともあり得ます。
取引する銘柄や時間帯の流動性にも注意を払うことが大切です。









7. メリット・デメリット徹底比較
CFD取引と先物取引、それぞれにどのような良い点と気をつけるべき点があるのでしょうか。このセクションでは、両者のメリットとデメリットを詳しく比較し、それぞれの取引方法がどのようなタイプの投資家に向いているのかを明らかにします。
7.1 CFDのメリットと注意点
CFD取引には、初心者の方にも魅力的な多くのメリットがあります。
メリット
- 少額から取引可能です。 先物取引に比べて、少ない証拠金で取引を始められる場合が多いです。
- 多様な銘柄に投資可能です。 国内外の株価指数、個別株、金や原油といった商品、さらには為替など、非常に幅広い資産クラスを取引対象にできます。
- 取引時間が長いことも特徴です。 多くの銘柄でほぼ24時間取引が可能なので、日中お仕事などで忙しい方でも、ご自身の生活スタイルに合わせて取引しやすいでしょう。
- 売りからも取引を開始できるため、価格が下落する相場でも利益を狙うチャンスがあります。
- 多くのCFDには決済期限がありません。 そのため、長期的な視点でポジションを保有することも可能です。
- 取引手数料が無料の場合が多いです。 その場合の主な取引コストは、売値と買値の差であるスプレッドになります。
一方で、CFD取引には注意すべき点もいくつかあります。
注意点
- レバレッジリスクです。 少ない資金で大きな取引ができる反面、予測が外れた場合の損失も大きくなる可能性があります。
- スプレッドの存在です。 取引手数料が無料でも、このスプレッドが実質的なコストとなります。市場の状況が急変した際には、スプレッドが通常よりも拡大することもあります。
- 金利調整額や価格調整額が発生することがあります。 ポジションを翌日以降に持ち越した場合、金利に相当する調整額や、原資産が先物の場合はロールオーバーに伴う価格調整額がかかることがあります。
- 情報収集の難しさが生じる場合があります。 特に海外のマイナーな個別株CFDなど、銘柄によっては日本語での情報が少なく、分析が難しいこともあります。
- 店頭CFDの場合、相対取引であることを理解しておく必要があります。 これは、取引所を介さず、証券会社が提示する価格で直接取引を行う形態です。そのため、取引所取引のような完全な価格の透明性とは異なる側面があります(カウンターパーティリスクとも呼ばれます)。
「取引手数料無料」という言葉だけに注目せず、スプレッドやその他の調整額を含めたトータルコストを考えることが大切です。
また、銘柄の選択肢が多いことはメリットですが、情報が少ない銘柄や理解の浅い銘柄に手を出すと、思わぬリスクを負うことにもなりかねません。









7.2 先物取引のメリットと注意点
先物取引にも、CFD取引とは異なるメリットと注意点があります。
メリット
- 取引所取引であることが大きな特徴です。 価格は市場の需給によって決まり、透明性が高く、公正な環境で取引が行われます。
- ヘッジ手段として有効に活用できます。 例えば、保有している株式ポートフォリオの価格下落リスクを避けるために、株価指数先物を売る、といった使い方ができます。
- CFDと同様に、売りからも取引を開始できるため、下落相場でも利益を追求できます。
- 株式の信用取引などと比較して、ポジション保有に関する金利負担がない場合が多いです。 ただし、証拠金として預けた資金の機会費用は考慮に入れるべきでしょう。
- CFDと同様に、レバレッジ効果により、少ない資金で大きな金額の取引が可能です。
一方で、先物取引特有の注意点も理解しておく必要があります。
注意点
- 取引単位が大きい傾向にあります。 CFDに比べて、一つの取引に必要な最低資金が大きくなることが多いです。例えば、日経225miniでも、CFDの日経225関連銘柄より大きな資金が必要になる場合があります。
- 取引期限(限月)が存在します。 限月までに決済するか、次の限月に乗り換えるロールオーバーという対応が必要になります。
- 取引手数料がかかります。 売買の都度、証券会社が定める手数料が発生します。
- 追証リスクがあります。 相場が不利な方向に大きく動いた場合、追加で証券会社に証拠金を差し入れる必要が生じることがあります。
- 仕組みがやや複雑に感じられるかもしれません。 初心者の方にとっては、限月やSQ(特別清算指数)、ロールオーバーといった先物特有の概念が難解に感じられることがあります。
取引所取引の透明性は大きな利点ですが、金利コストがない代わりに、限月管理やロールオーバーの手間とコストが発生します。
CFDがこれらの手間を金利調整額などで吸収しているのと対照的です。









7.3 CFDが向いている投資家タイプ
CFD取引は、特に以下のような特徴を持つ投資家の方に向いていると言えるでしょう。
- 投資初心者の方です。 比較的少額の資金から取引を始めることができ、仕組みも先物取引に比べると分かりやすい部分があるため、最初のステップとして適している場合があります。
- 少ない資金で取引を始めたい方です。 レバレッジを活用することで、手元の資金以上の金額の取引に挑戦でき、多様な銘柄にアクセスしたいと考える方にも良いでしょう。
- 日中お忙しく、夜間や早朝に取引したい方です。 多くのCFD銘柄はほぼ24時間取引が可能なので、ご自身のライフスタイルに合わせて取引時間を柔軟に選べます。
- 柔軟な取引期間を望む方です。 多くのCFDには決済期限がないため、相場の状況を見ながらじっくりとポジションを保有したり、逆に短期で売買を繰り返したりと、自由な戦略を立てやすいです。
- 様々な市場に分散投資をしたい方です。 株式、株価指数、商品、為替など、一つの口座で手軽に多くの市場にアクセスできるため、リスク分散を図りたい方にも便利です。
CFDの持つ「柔軟性」、つまり決済期限のなさ、24時間近い取引時間、多様な投資対象といった点は、特に初心者の方や日中忙しい方にとって大きな魅力となります。
ただし、CFDが手軽に始められるからといって、リスク管理の学習を怠ってはいけません。
レバレッジ取引である以上、損失が預けた証拠金を上回る可能性も理解した上で、慎重に取引を始めることが大切です。









7.4 先物取引が向いている投資家タイプ
一方で、先物取引は以下のような特徴を持つ投資家の方により適していると考えられます。
- ある程度投資経験がある中〜上級者の方です。 市場の相場観を養い、ご自身で判断する力や、しっかりとしたリスク管理能力が求められるためです。
- まとまった資金で取引できる方です。 CFDに比べて取引単位が比較的大きいため、ある程度の資金力がある方が取り組みやすいでしょう。
- 特定の指数や商品を専門的に取引したい方です。 例えば、日経225先物や金先物など、流動性が高く市場参加者も多い主要な先物市場で、集中的に取引を行いたいと考える方です。
- ヘッジ取引を積極的に行いたい方です。 保有している現物資産の価格変動リスクを回避する目的で、先物市場を利用する投資家の方です。
- 取引の透明性を重視する方です。 取引所で行われる取引のメリット、つまり公正な価格形成や約定の透明性を重視する方に向いています。
- 短期間での値動きを予測して利益を狙いたい方(決済期限を意識できる方)です。 先物取引には限月があるため、その期限を意識した上で、短期的な価格変動を捉えて取引できるスキルがある方です。
先物取引は、一般的にCFDよりも大きな資金が必要となり、限月の管理など運用上の手間もかかります。
そのため、市場の仕組みをよく理解し、自己資金やリスク許容度を把握した上で、計画的に取引できる経験と知識を持つ投資家の方に適していると言えるでしょう。









8. 実践ガイド:CFDと先物どちらを選ぶ?
実際に取引を始めるにあたり、CFDと先物取引のどちらを選べば良いのでしょうか。このセクションでは、あなたの投資目的やスタイルに合わせた選び方のフロー、ニュースやイベント時の取引のコツ、具体的な銘柄での比較、そして取引プラットフォームや証券会社の選び方まで、実践的なガイドを提供します。
8.1 目的別の選択フロー
CFDと先物取引、どちらを選ぶべきか迷うのは当然です。
ご自身の投資目的や状況に合わせて、最適な方を選ぶための簡単なフローを考えてみましょう。
以下の質問にご自身で答えてみてください。
- 投資に使える資金はどのくらいですか。
- 数万円程度の少額から始めたい → CFDが向いているかもしれません。
- ある程度まとまった資金(数十万円以上)を準備できる → 先物取引も選択肢に入ります。
- 投資の経験はどのくらいありますか。
- 投資は初めて、またはまだあまり経験がない → CFDから始めるのが良いかもしれません。
- ある程度投資経験があり、市場の動きにも慣れている → CFD、先物取引のどちらも検討できます。
- どのような商品を取引したいですか。
- 国内外の株価指数、個別株、商品など、多様な商品に手軽に投資したい → CFDが便利です。
- 日経平均やNYダウ、金や原油など、特定の主要な商品に集中して取引したい → 先物取引も有力な選択肢です。
- ポジションをどのくらいの期間保有したいですか。
- 短期から中期で柔軟に売買したい、または長期的にじっくり保有したい → 決済期限のないCFDが適している場合があります。
- 取引期限を決めて計画的に取引したい、またはロールオーバーの管理もできる → 先物取引も考えられます。
- 取引コストについてどのように考えますか。
- 取引ごとの手数料を抑えたい(スプレッドは許容できる) → CFDが良いかもしれません。
- スプレッドよりも手数料体系が明確な方が良い、または大口取引でのコストを重視する → 先物取引が有利な場合があります。
- 取引の自由度とルールの厳格さ、どちらを重視しますか。
- 取引時間や銘柄選択など、自由度の高さを求める → CFDが向いています。
- 取引所が定める厳格なルールのもとで取引したい → 先物取引が適しています。
これらの質問への答えを総合的に見て、ご自身にどちらの取引方法がより合っているかの方向性が見えてくるでしょう。
投資の目的やスタイルは時間と共に変化することもあります。
最初はCFDで経験を積み、将来的に先物取引にも挑戦するというステップも考えられます。









8.2 ニュース・イベントトレードのコツ
経済指標の発表時や、各国の中央銀行による金融政策の変更などのニュースやイベントがあるときは、市場価格が大きく変動しやすいタイミングです。
このようなときに取引(ニュース・イベントトレード)を行う際のコツと注意点をお伝えします。
まず、事前の準備が非常に重要です。
- 発表される経済指標の重要度や、市場参加者がどのような数値を予想しているか(市場予想)を調べておきましょう。
- 過去に同様の発表があったとき、価格がどのように反応したかを確認しておくのも参考になります。
- どのような結果が出たら、価格がどちらの方向に、どの程度動きそうか、いくつかのシナリオをあらかじめ立てておくと冷静に対応できます。
次に、リスク管理をいつも以上に徹底する必要があります。
- ニュースやイベント時は、通常よりも価格の変動幅(ボラティリティ)が大きくなることが多いため、レバレッジを抑えめにするか、取引する数量を少なくすることを心がけましょう。
- 万が一、予測と反対の方向に価格が急変した場合に備えて、必ず逆指値注文(ストップロス注文)を設定し、損失の範囲を限定しておくことが不可欠です。
- このようなときは、スプレッド(売値と買値の差)が通常よりも拡大しやすく、スリッページ(注文価格と約定価格のズレ)も発生しやすくなります。証券会社によっては許容スリッページを設定できる機能があるので、活用するのも一つの方法です。
取引のタイミングも重要です。
- 指標発表の直後は、価格が非常に荒い動きをすることが多いです。そのため、少し時間が経って市場が落ち着いてからエントリー(新規注文)するのも有効な戦略です。
- 相場には「噂で買って事実で売る(またはその逆)」という格言があります。ニュースが出る前に期待感で価格が動き、実際にニュースが出ると反対方向に動くこともあるので、そういった値動きのパターンも意識しておくと良いでしょう。
CFDは多様な銘柄にアクセスでき、売りからも取引を始められるため、様々なニュースやイベントに応じて柔軟に対応しやすいという側面があります。
もし、ニュース・イベントトレードに挑戦してみたい場合は、まずはデモトレードで練習し、値動きの感覚を掴んでから、少額で実際の取引を始めてみるのが良いでしょう。









8.3 日経225CFD vs 日経225先物の実例
日本を代表する株価指数である日経平均株価(日経225)を例にとって、CFD取引と先物取引が具体的にどのように違うのかを見ていきましょう。
以下に、日経225を対象としたCFD(例:楽天CFDのJP225.mt4)と、日経225先物(例:日経225mini)の主な特徴を比較した表を示します。
| 特徴 | 日経225 CFD (例: 楽天CFD JP225.mt4) | 日経225先物 (例: 日経225mini) |
| 取引単位 | 価格の1倍 (例) | 指数価格の100倍 |
| 呼値 | 0.1円 (例) | 5円 |
| 最低必要資金(目安) | 数千円〜 (レバレッジ10倍として) | 数万円〜 (レバレッジ約20-30倍として) |
| 取引手数料 | 無料 (スプレッドあり) | 有料 (例: 1枚あたり30円〜50円程度) |
| レバレッジ | 最大10倍 (例) | 約20〜30倍 (市況により変動) |
| 決済期限 | なし | あり (3月、6月、9月、12月など) |
| 取引時間 | ほぼ24時間 | 日中・夜間 (例: 8:45-15:15, 16:30-翌6:00) |
| ロスカット | 証拠金維持率100%以下で発動 (例) | 追証解消不可時に強制決済 |
この表の各項目について、もう少し詳しく見てみましょう。
取引単位が大きく異なります。
CFDでは日経平均株価の価格の1倍から取引できるのに対し、日経225miniでは指数価格の100倍が1枚の取引単位となります。
この違いは、同じ値動きでも損益の大きさに直結します。
例えば、日経平均株価が100円動いたとします。
日経225CFD(取引単位1倍)を1単位保有していた場合、損益の変動は100円×1倍で100円です。
一方、日経225miniを1枚保有していた場合、損益の変動は100円×100倍で10,000円となります。
このように、先物取引の方が、一般的にCFDよりも大きな資金とリスクを取ることになります。
最低必要資金も、CFDの方が少額で済む傾向があります。
取引手数料は、CFDが無料(スプレッドが実質コスト)であるのに対し、先物取引では売買ごとに手数料がかかります。
レバレッジは、CFDが最大10倍程度(銘柄による)であるのに対し、先物取引は相場の状況によって変動しますが、より高いレバレッジをかけられる場合があります。
決済期限の有無も大きな違いです。CFDには基本的にありませんが、先物には限月があり、期限までに決済する必要があります。
取引時間は、CFDの方がより長く、ほぼ24時間取引できる銘柄が多いです。
これらの違いを理解することで、ご自身の資金量やリスク許容度、取引スタイルに合った方を選びやすくなるでしょう。









8.4 取引プラットフォームと証券会社比較
CFD取引や先物取引を実際に始めるには、これらの取引サービスを提供している証券会社で専用の口座を開設する必要があります。
どの証券会社を選ぶかは、今後の取引のしやすさやコストに大きく関わってくるため、慎重に比較検討しましょう。
証券会社を選ぶ際に注目したい主なポイントは以下の通りです。
- 取扱銘柄
- ご自身が取引したいCFDの銘柄(株価指数、個別株、商品など)や、先物の種類(日経225mini、TOPIX先物など)を取り扱っているかを確認しましょう。
- 取引コスト
- CFDの場合:スプレッド(売値と買値の差)の狭さ、ポジションを翌日以降に持ち越す際にかかる金利調整額や価格調整額などを比較します。
- 先物取引の場合:売買ごとにかかる取引手数料の安さを比較します。
- 取引ツール
- パソコン用の取引ツールやスマートフォン用のアプリの使いやすさは非常に重要です。チャート機能が充実しているか、注文方法が分かりやすいか、動作は安定しているかなどを確認しましょう。MT4(メタトレーダー4)という高機能な取引プラットフォームに対応しているかもポイントになることがあります。
- 情報提供・サポート体制
- 市場に関するニュースや分析レポートなどの情報提供が充実しているか、初心者向けの学習コンテンツやセミナーが用意されているか、困ったときの問い合わせ対応が親切で迅速かなども確認しましょう。
- 会社の信頼性・安全性
- 金融庁に登録されている正規の業者であるか、顧客の資産がどのように管理(信託保全など)されているかなど、会社の信頼性や安全性も大切なチェックポイントです。
- 最低入金額・取引単位
- 特に初心者の方は、少額から無理なく始められるかどうかも重要です。最低入金額や最小取引単位を確認しましょう。
- デモ口座の有無
- 多くの証券会社では、実際の資金を使わずに本番さながらの取引を体験できるデモ口座を提供しています。取引ツールの操作感や値動きを試すために、デモ口座があるかどうかは必ず確認しましょう。
CFD取引で人気の証券会社としては、例えばGMOクリック証券(特に株式CFDに強く、スプレッドの競争力も高いと言われています)や、IG証券(取扱銘柄数が非常に多く、特に商品CFDに強いと言われています)などがあります。
先物取引は、SBI証券、楽天証券、松井証券といった主要なネット証券の多くで取り扱っています。
最終的には、ご自身の取引スタイルや投資目的、重視するポイントなどを総合的に考えて、最適な証券会社を選ぶことが大切です。
焦らずに情報を集め、比較検討してみてください。









9. CFDと先物を併用した戦略例
CFD取引と先物取引は、それぞれ単独で使うだけでなく、組み合わせて利用することでより高度な戦略も可能になります。このセクションでは、ヘッジ取引の具体例、裁定取引(アービトラージ)の基本的な考え方、そして中長期的なポジションを管理するローテーション戦略について紹介します。これらは少し応用的な内容ですが、将来のステップアップのために知っておくと役立つでしょう。
9.1 ヘッジ取引の組み合わせ
ヘッジ取引とは、すでに保有している資産(例えば株式や投資信託など)の価格が変動することによって生じるリスクを抑えるために、その資産と反対の値動きをするような別の取引を行うことです。
CFDと先物取引は、このヘッジ取引に活用できます。
例1:株式ポートフォリオのリスクヘッジ
例えば、あなたが日本の個別株をいくつか保有しているとします。
今後、日本市場全体が下落するのではないかと心配になった場合、どうすれば良いでしょうか。
このようなとき、日経225先物を売り建てる(空売りする)か、日経225CFDで売りのポジションを持つことで、ヘッジが可能です。
もし実際に株価が全体的に下落した場合、保有している株式の価値は下がってしまいます。
しかし、同時に日経225先物やCFDの売りポジションからは利益が出るため、株式の損失をある程度相殺することができるのです。
例2:CFDと先物の使い分け
ヘッジ取引を行う際にも、CFDと先物を状況に応じて使い分けることができます。
例えば、大きな資金で、比較的長期的な視点でポートフォリオ全体のリスクをヘッジしたい場合はどうでしょう。
この場合は、取引単位が大きく、流動性も高い主要な先物(例えば日経225ラージ先物など)を利用するのが適しているかもしれません。
一方で、ポートフォリオの中の一部の銘柄だけを細かくヘッジしたい場合や、短期的な市場の調整に対応したい場合はどうでしょうか。
この場合は、より小回りが利き、多様な個別株CFDやミニサイズの指数CFDなどを利用する方が便利かもしれません。
CFDは決済期限がないものが多いため、長期的なヘッジポジションをロールオーバー(乗り換え)の手間なく保有しやすいというメリットもあります。
ただし、その場合は金利調整額などの保有コストに注意が必要です。
CFDの細かさと柔軟性、先物の市場規模と標準化された特性を理解し、目的に応じて使い分けることで、より効果的なヘッジ戦略を組むことが可能になります。









9.2 裁定取引(アービトラージ)の基本
裁定取引(アービトラージ)とは、理論的には同じ価値を持つはずの商品が、異なる市場で一時的に異なる価格で取引されている場合に利用される手法です。
具体的には、割安になっている方を買い、同時に割高になっている方を売ることで、価格差から利益を得ようとするものです。
市場の価格の歪みを利用する取引とも言えます。
CFDと先物の間でのアービトラージの例
例えば、ある株価指数を対象としたCFDの価格と、同じ株価指数を対象とした先物の価格との間に、一時的に理論的におかしいと考えられる価格差(歪み)が生じたとします。
仮に、CFDの価格が先物の価格よりも割安になっていると判断した場合、CFDを買い、同時に同じ価値分の先物を売ります。
その後、CFDと先物の価格差が理論的に正常な水準に戻った時点で、それぞれ反対売買(CFDを売り、先物を買い戻す)を行うことで、最初の価格差分の利益を確定するという考え方です。
注意点
しかし、現代の金融市場は非常に効率化されています。
テクノロジーの進歩により、このような価格差は発生したとしてもごく短時間で解消されてしまうことがほとんどです。
そのため、アービトラージで利益を得る機会は非常に少ないか、あったとしてもごくわずかなものとなっています。
また、実際にアービトラージを実行するには、高度な取引システムと、極めて低い取引コスト(スプレッドや手数料)が不可欠です。
そのため、個人投資家がCFDと先物を使ってアービトラージを実践し、継続的に利益を上げるのは極めて難しいと言わざるを得ません。
このような取引手法があるという知識として知っておく程度で良いでしょう。
初心者のうちは、価格の方向性を予測する取引や、前述したヘッジ取引など、より現実的な戦略に集中することをおすすめします。









9.3 中長期ポジションのローテーション戦略
中長期的な視点で、特定の市場に対して強気(価格が上がると予測)または弱気(価格が下がると予測)のポジションを持ち続けたいと考える場合に、CFDと先物を巧みに使い分ける戦略があります。
これをポジションのローテーション戦略と呼ぶことにしましょう。
例:日経平均株価に長期的に強気な場合
あなたが今後、日経平均株価は長期的に上昇すると考えているとします。
この場合、以下のような戦略が考えられます。
- コアポジション(中心となる大きなポジション)資金効率や取引コストを考慮し、日経225先物(例えば日経225miniや日経225ラージ)で、比較的大きな買いポジションを構築します。先物には限月があるため、期限が近づいてきたら、次の限月の先物に乗り換えるロールオーバーを行い、ポジションを維持し続けます。
- サテライトポジション(調整用の小さなポジション)コアとなる先物のポジションは動かさずに、短期的な価格の動きに対応するためにCFDを活用します。例えば、一時的に価格が下がった(押し目)ところで追加の買いを入れたい場合や、短期的に利益が出た部分だけを確定したい場合に、より小口で機動的に取引できる日経225CFDを利用します。CFDなら、先物の大きなポジションに影響を与えることなく、細かく売買の調整ができます。また、先物のロールオーバーを行う期間中に、一時的にCFDで買いポジションを代替しておくといった使い方も考えられます。
CFDは決済期限がないものが多いため、ロールオーバーの手間やコストを避けたい場合に、中長期のポジションをCFDだけで保有するという選択肢もあります。
ただし、その場合は金利調整額などの保有コストが継続的にかかることを考慮する必要があります。
このローテーション戦略は、CFDと先物それぞれの商品の特性、つまりコスト構造、取引単位の大きさ、限月の有無などを深く理解した上で、状況に応じて柔軟に使い分ける、やや応用的な考え方です。
しかし、将来的に大きな資金を運用するようになったり、より精緻なポートフォリオ管理を目指したりする際には、役立つ視点となるでしょう。









この記事では、CFDと先物取引の主な違いを、取引期限、取引形式、取扱銘柄、コスト、レバレッジなど多角的に解説しました。
CFDは取引期限がなく多様な銘柄を少額から始められる一方、先物は特定の期間に集中して取引したい場合に適しています。
それぞれの特性を理解することで、リスクを抑えつつ効率的な資産運用が可能になります。
ご自身の投資目的やスタイルに合った取引方法を選び、一歩踏み出してみませんか?
本記事の注意事項(免責事項)
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘を意図したものではありません。本記事に記載されている情報については、正確性、完全性、有用性を確保するために努力しておりますが、その保証は致しかねます。投資判断はご自身の責任で行ってください。本記事の内容を利用して生じたいかなる損害についても、当サイトおよび著者は一切の責任を負いかねます。詳しくは免責事項ページをご確認ください。



最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
【登場人物】






【関連記事】
※CFD:差金決済取引